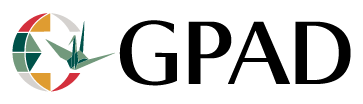緊急人道支援から平和構築への移行期に持続可能な解決策を:浅木⿇梨耶さん
- 浅木⿇梨耶さんは、日本出身の開発分野の専門家で、教育および人道支援に従事しています。
- 外務省による「平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業」(広島大学受託、国連訓練調査研究所(ユニタール)および国連ボランティア計画(UNV)協力)の2024年度プライマリー・コースに参加しました。
- この研修を通じて、⿇梨耶さんは危機管理や国連システムについての知見を深めました。現在派遣されているヨルダンでの国連ボランティアとしての活動において、平和に向けた持続可能な解決策を模索しながら、この研修で得た知識を実践に移そうとしています。
2025年6月・広島-日本出身の浅木⿇梨耶さんは、過去7年間にわたり、アフガニスタン、ラオス、ミャンマーにおいてNGO職員として教育および人道支援に従事してきました。国連で働きたいという想いから、2025年1月から2月にかけて、オンラインおよび広島と東京で開催された「平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業」プライマリー・コースに参加しました。
この事業は、外務省により実施されており、2024年度から広島大学が外務省の委託を受け、国連訓練調査研究所(ユニタール)および国連ボランティア計画(UNV)と協力して運営しているものです。
紛争解決と復興の複雑さを学ぶ

アフガニスタンとミャンマーで活動する中で、⿇梨耶さんは、社会的再統合、物理的再建、制度構築といった紛争後の各段階や、その背景にある構造を十分に理解しないまま活動することの限界を痛感しました。
人道支援の現場では、紛争後の脱構築の段階を理解することがとても大切だと感じています。それは、一時的な支援だけではなく、持続的で根本的な解決につながる取り組みが求められるからです。今後このような課題に挑戦していきたいです。
浅木⿇梨耶
プライマリー・コース研修修了生、日本
プライマリー・コースを修了した今、緊急支援や開発援助の現場で活動するための自信を持てたと感じています。対話型のセッションやグループワークを通じて、危機管理に関する貴重な学びを得ることができました。また、この研修を通じて、他者の意見を深く聞き、多様な意見をまとめるといったコミュニケーションスキルが、平和構築に携わる者にとって不可欠であるということ再認識しました。
広島平和記念資料館を訪れた際には、言葉を失いました。「人によって“平和”の定義は異なる。ある人は平和のために戦い、また別の人は正義のために戦う。平和は外部から押し付けられるようなものではないし、平和を促進するには「平和」の理解が欠かせない。」-そんな複雑な現実に改めて思いをはせました。

研修員同士の支え合い
知識やスキルに加えて、⿇梨耶さんがこの研修で得たものは、研修員同士のつながりだったと語っています。
もともと研修には、様々な考えや知識、スキルを得ることを期待していました。ですが、実際には他の研修員たちから学ぶこともとても大きく、学び合いの場として多くの方が参加されるといいと思います。スキルや知識を得るだけでなく、ネットワークを築く機会として。仲間との関わりや助言、支えが、自分のキャリアを目指す大きな原動力になっています。
浅木⿇梨耶
プライマリー・コース研修修了生、日本
⿇梨耶さんは、それぞれの研修員がキャリアを歩んでいく中で、この新たに築かれたネットワークが今後も情報やリソースを共有し、お互いを支える場になると期待しています。
国連での活動に向けて

4週間の研修を修了した⿇梨耶さんは、ヨルダンの国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)に准プログラム担当官として1年間派遣されます。派遣中は、プライマリー・コースで学んだ国連システムの仕組み、使命や役割に関する知識を、実務の中で活かしたいと考えています。国連ボランティアとしての活動においても、平和構築のプロセスは直線的ではなく、現場の状況に応じて柔軟に対応する必要があるという意識を忘れずに、常に平和的なアプローチを心がけたいと思っています。この研修を通じて、⿇梨耶さんは開発分野の専門家としてのキャリアを築くことへの自信がより高まったと感じています。
今後、緊急人道支援から平和構築への移行期において、持続可能な解決策を提案できるように努めたいと考えていて、すべての人が尊厳と安心のもとに生きられる、より公正な世界の実現に貢献したいという思いを胸に活動を続けていきます。
まだまだ手探りの部分も多いですが、現場での活動を通して貢献できることにやりがいを感じています。難民の方々を取り巻く不安定な情勢が支援の在り方にも影響を与えている現状を目の当たりにし、戸惑うこともありますが、自分にできることを一つ一つ積み重ねていきたいと思います。
浅木⿇梨耶
プライマリー・コース研修修了生、日本
外務省「平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業」について
麻生太郎外務大臣(当時)の政策演説「平和構築者の『寺子屋』を作ります」を受け、2007年から外務省が平和構築分野の人材育成事業を実施。2015年度からは、国際機関での人材の発掘・育成・キャリア構築を包括的に実施するため事業内容を刷新・拡大し、「平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業」を開始。2024年度から、広島大学が外務省より委託を受け、国連ユニタールおよび国連ボランティア計画と協力して事業の実施・運営を行っています。
広島大学について
広島大学は、人類史上初めて原子爆弾が投下された被爆地広島に1949年に創設された国立の総合研究大学です。広島大学は、国立大学としての使命を果たすため、活動の基本原則として広島大学憲章を次の通り定めています。それは、一人ひとりの人権と人格を尊重し、自由で平和な持続的発展を可能とする社会の実現に貢献する人材を育成し、社会に開かれた大学、社会から信頼される大学として地域社会及び国際社会に貢献することです。さらに地球規模の課題に対する先端的な解決策を世界に先駆けて実践していきます。これにより広島大学の使命である、多様性を育む自由で平和な国際社会の実現に貢献する「平和を希求しチャレンジする国際的教養人」を育成することを目指します。
国連ボランティア計画について
世界中でボランティアリズムを通じて平和と開発に貢献する国連ボランティア計画(UNV)は、パートナーと連携し、資格を持ち、高い意欲と十分な支援を受けた国連ボランティアをさまざまな国連機関に派遣しています。その中でもプライマリー・コースでは日本人研修員を国連ボランティアとして海外派遣する業務を実施しています。本事業を通じて2007年以降に派遣された国連ボランティアの総数は、200名以上にのぼります。派遣先は、コートジボワール、エチオピア、ギニア・ビサウ、ケニア、リベリア、ルワンダ、シエラレオネ、南スーダン、タンザニアを含む50以上の国・地域に及びます。主な派遣先機関は、UNDP、UNHCR、UNICEF、IOM、WFPです。
国連ユニタールについて
国連訓練調査研究所(ユニタール)は、研修事業に特化した国連機関です。2024年には、世界中で55万人以上が受講し、より良い未来の実現のために世界各国の人材育成を支えています。ジュネーブ本部のほか、広島、ニューヨーク、ボンに事務所を構え、世界中にネットワークを持っています。詳しくは国連訓練調査研究所(ユニタール)広島事務所をご覧ください。